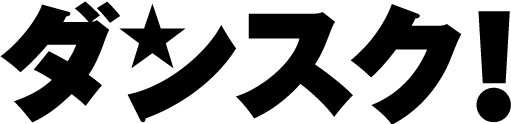妥協せずに踊り進んでいく【菅原小春】がブルーノート東京ソロ公演で見せた「問いかけ」
2022.09.14 DANCE
菅原小春は、問いかける。
貴方は私のように踊っているだろうか。
こんな動きで、こんな形で、こんな眼で、こんな気持ちで——。
幼少の頃からダンスコンテストで有名になった彼女は、当時から圧倒的に他と違っていた。
ステージ上から審査員を睨みつけ、観客を挑発し、120%の本気をブツけ、その場の空気をさらっていった。
そして、その存在は見る者に強く問いかける。
貴方は私のように踊っているだろうか。
貴方は私のように生きているだろうか——。

今年で30歳を迎えた菅原小春は、6年ぶりのソロ公演『SUGAR WATER』をジャズの殿堂ブルーノート東京にて、9月初めの2日間公演で開催した。
実姉を含む生バンドとダンサー、俳優をキャスティングし、童話的なストーリーと偶発的なライブ展開で繰り広げられる独自のパフォーマンスは、今の彼女の等身大を映し出す、ハッピーでファニーで、愛に溢れたものだった。
そこには、怒りや焦燥感をエネルギー源に、まるで戦うように踊っていた、かつての彼女の姿はない——。
菅原小春は、戦う。
「私、小さい頃から“自由探し”をしていたんです。千葉の海の街で生まれて、気づいたら自然に踊っていて、自然に創作をして、ダンスの中で自由さを感じていたんだと思います。それを披露して認めてもらえる場所が、当時はコンテストしかなかった。だから出ていたんですけど、小中高と続けてそのうちにコンテストの勝ち方がわかってきて、“あれ、私何のために踊ってるんだろう?”って、不自由さを感じるようになってきた。そして、海外に行って新しい自由を見つけた。言葉が通じなくても、踊りで繋がれる。踊りで会話ができるっていう自由さを、そこで見つけたんです」
高校卒業後には単身アメリカへ。
一人で、本気で、捨て身で、自分を晒し、飛び込ませる。
彼女のダンスは徐々に話題を呼び、SNSで拡散しながら、瞬く間にヨーロッパなど世界各地へ広がっていった。ワークショップやイベント出演のラブコールを次々に受け、世界を飛び回る日々。アーティストのバックアップやコレオグラフ、CM・MV出演、ハイブランドのモデルや女優業などを通じて、「KOHARU SUGAWARA」の名は国内外の一般層までに拡散していく。
菅原小春のダンスはすごい/ダンサーの可能性を広げた/ダンスを超えた表現だ/彼女はアーティストだ/新時代を象徴する強くてカッコいい女性像だ……etc.
「ヨーロッパやアメリカを行き当たりばったりで7年ぐらいグルグル回って、月に5回ぐらい海外の往復みたいなことをやっていたら……、だんだん心も体もキツくなってきた。有名になりたくて、必死で前に進んできて、実際に有名になれて、何だか芸能人みたいな見られ方になって、知らない人からいろんなことを言われるようになって……、有名にはなったけど逆に孤独感が深まって、だんだんと疲れてきた。好きで踊ってきたダンスがお金に変換されたり、私の人を見る目が変わってきたり、そういうことに自分が“自然に”おかしくなってきたんです」

菅原小春は、捨てる。
20代前半を駆け抜け、さまざまなアーティストとの共演をこなす中、『パプリカ』での共演することになるコンテンポラリーダンサー辻本知彦との出会いがあった。25歳、その出会いが彼女を一気に楽にさせ、解放させた。
「初めて会った時に“お前、ダンス下手だな”って言われて、“面白いな、この人”って思ったんです。私も自分のダンスや、求められるイメージに飽きてきた頃だったから、辻本さんの現場に2年ぐらいついてまわって、あの人のノールールぶりを吸収した。そして、捨てれたんです。下手と言ってくれることで、それまでの自分のダンスを捨てれた。良いきっかけでした」
捨てることとは手放すこと。
執着、自我、自尊心、柵(しがらみ)、過去、そして自分自身をも。
手放すことによって解放され、無の境地に近づき、スペースが生まれ、新しい自分が入ってくる。
「最近考えるのが、自分を無くすということは、自分が在るということなんだなって…。自分を持っているということは自分が無いということ。表現をやっている人って、裸になって、自分を捨てて、やがて自分が在るのか無いのかわからない状態になる。在るんだけど無い——そこは一生模索していくところなんだと思います」
在るようで無い。自分無くしが自分探し。まるでZENの境地の如く。
菅原小春の自己探求への旅はコロナを経て、次のステップを踏んでいく——。